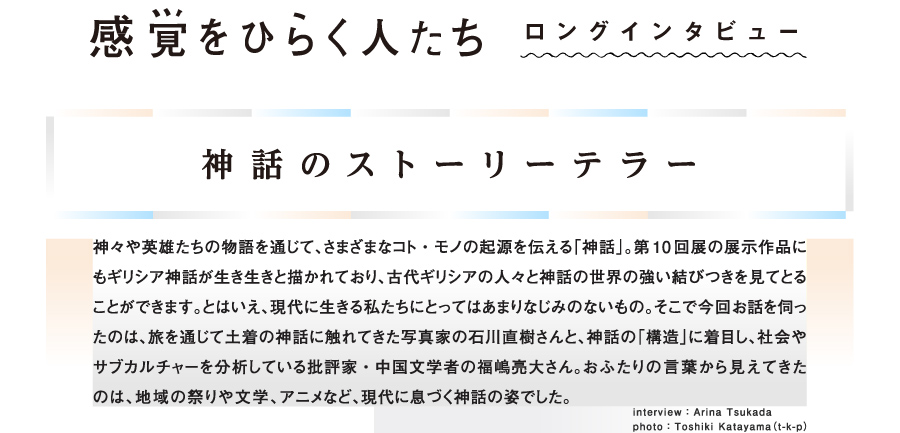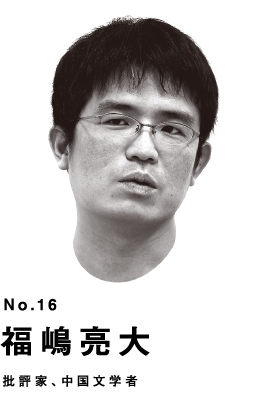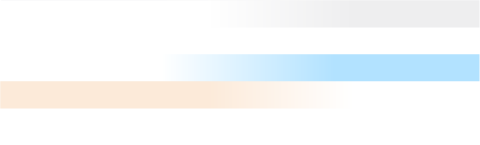資本主義社会の中で、
神話の代替を果たすもの。
── 福嶋さんは神話の「構造」に着目した視点から現代の文化について言及されていますが、神話がもつ役割とは一体何なのでしょうか?
一言でまとめると、「世界の成り立ちや起源を示すこと」ですね。この意味での神話は、古代社会に限らず、現代でも必要になる場合があるんです。たとえば、アメリカ社会の起源には独立宣言があり、フランス社会の起源には一連の革命がある。で、国家が危機や混乱に陥ったときには、それらの出発点に立ち返って、あらためて自分たちの在りかたを反省することができるというわけです。
ところが、今日の資本主義はあらゆるものを相対化し、流体化してしまうので、誕生と破壊のサイクルがどんどん高速化する。そのために「たったひとつの起源」という神話的な語りは、そのままではリアリティがなくなってしまいます。こういう流体的な世界に対応するかたちで、かつての英雄や革命のイメージではなく、もっと卑俗な美術や文学などのコンテンツが神話の代替を果たすことになるんです。
── 神話の代替を果たしているものとして、具体例はありますか?
たとえば、村上春樹さんの小説にはよく年号が入っていますね。1980年に出た『1973年のピンボール』だと、時代設定を1973年に巻き戻し、そのかりそめの「起源」から世界をリスタートする。ゼロ年代に書かれた『1Q84』も同じ手法ですね。なかば忘れられた近過去にさかのぼり、そこからあらためて社会の成り立ちを検証する。村上氏は流体化した資本主義社会において、私的でマイナーな神話を書いたわけです。
── 現代の日本だからこそ、生まれた神話ということでしょうか。
今日の社会では、ものすごいスピードで破壊と再生が繰り返されているために、我々は何かをなくしたという記憶もなくしちゃうんですね。つまり、喪失自体が抽象化している。それは実は震災後の状況も同じであって、日本人の心理としては、おそらく単に街が破壊されたという以上の何かを失っているはずなんですよ。しかし、それが何なのか具体的にわからないので「喪の作業」に入れない。だから、フロイト的にいえばメランコリー(鬱)に陥る。こうした「抽象的喪失」が常態化してしまうと、もはやかつてのギリシア神話のような英雄叙事詩は機能しなくなる。メランコリーの時代に対応した、新しいタイプの神話が必要なんです。
精密さと珍妙さの「落差」を求める、
現代日本の新たな神話。
── “新しいタイプの神話”とはどのようなものですか?
文明化が進むと、荒々しい感情や暴力衝動がそれなりにコントロールできるようになる。心理学者のスティーブン・ピンカーの著書『The Better Angels of Our Nature』なんかでも、人類の暴力傾向は減少しつつあると定量的に分析されている。しかし、そういう精密化した社会においても、ひとたびシステムエラーが起こると、制御不可能な、何か恐るべきものが立ち上がってくるわけで、その「落差」をキャッチすることが重要ではないかと思うんです。
たとえば、村上隆さんのアートは技術的なレベルで極めて精密に作られている一方、そこから現れてくるものは非常に珍妙な“バケモノ”です。確実性がそのまま不確実性に連続するとか、あるいは精密なシステムがそのまま珍妙な怪物にオーバーラップしていくといった、“二重性を外化する”ことが、今日に必要な神話的表現ではないでしょうか。逆に、単にきっちり作りましたとか、単に暴力や怒りを描いてみましたとか、そういうものにはあんまり魅力を感じないですね。坪内逍遥じゃないけれど、やっぱり「雅俗折衷」が日本的表現の肝だと思います。
── それは、アニメやマンガなどのサブカルチャーにも現れているのでしょうか。
個別のコンテンツ以上に、まずは戦後の日本社会の特性を見ないといけない。坂口安吾の「堕落論」ふうにいえば、戦場で輝かしい死を迎えるはずだった特攻隊員が、死に損ねてヤミ屋になってしまったという問題です。戦後日本はみじめな「堕落」が起源にある国なんですよ。実際日本人は、原爆という人類史的悲劇のあとに鉄腕アトムやゴジラのようなエンタメを作ってしまったわけで、こんなひどい堕落はほかにはちょっと例を見ません(笑)。原爆ドームですら「文化遺産」といってしまうほど、滅亡に対するリアリティが根本的に欠けている。結局、戦後日本社会でマンガが流行ったという以上に、戦後日本社会そのものがズッコケた「マンガ」なのだし、それこそが我々の神話的起源というものではないかと思うんです。ただ、それがよいかどうかは別問題で、何でもかんでも文化遺産にしてしまう風土を全面肯定する気にもなれないですが。
── “マンガ的な社会”とはおもしろい表現ですね。こうした土壌で、ほかにはどんな作品が生み出されていると思いますか?
最初からズッコケていて地に足がついていないからこそ、既存のものを大胆にハッキングできるということもあります。特に、宮崎駿さんはディズニーアニメに反発した作家ですね。もともと気候が厳しいアメリカ中西部で生まれたディズニーは、一切の荒ぶる自然を排除しようとする、きわめてアメリカ的な欲望に動かされていた。そして、その欲望から清潔なディズニーランドが出てくるわけです。それに対して、ディズニー以降のアニメ史の中でいわば「幽霊化」した自然を呼び戻そうとしたとき、『ナウシカ』の腐海や『ポニョ』の津波みたいに、マンガと災厄がごっちゃになった自然が立ち上がってくる。宮崎アニメは、日本アニメの植民地化に対するひとつの挑戦でもあるんですね。この点で、宮崎氏はまさにポストコロニアルな作家なんです。そして、宮崎アニメがやったような大胆な書き換えが可能なのも、もともとの文化や社会そのものが「マンガ的」にできているからでしょう。
「愛」より「恋」が
日本人の重要ファクター。
── 過去、神話を生み出した聖地へ実際に行かれたことはありますか?
最近は暇さえあれば旅行しています。それで思うのは、日本の古代文学はやっぱり現地を歩いてみないと理解できないということ。まあ、歩いても理解できるかどうかはあやしいですが(笑)、歩いてみないと絶対にわからない。『万葉集』はその編纂時点での「古都」、つまり今でいう明日香村や桜井市を多く扱った歌集ですが、その故地を歩くと、日本の地形のもつ無邪気さが文学に深く刻み込まれているという印象をもちます。攻撃的なところが一切ない、なだらかな山並みに囲まれた空間があって、そこに陽の光が燦々と無邪気に降り注いでいる。まさに「山ごもれる大和しうるはし」というやつで、その温和な風景は原爆ドームを「文化遺産」にしてしまう無邪気さとも遠く響き合っていると思います。
ただ、その一方で、現代においては文化領域全般が脱地理化しているという問題もあります。よくいわれるように、グローバル化や資本主義化が進むと、どの土地の空間も似たり寄ったりになってくる。そうすると、今度は時間のほうで差異を出していこうということにもなるわけですね。
“時間の要素で差異を出していく”ことの一例として、演劇があります。ここ何年かで日本の若手の演劇を観るようになったんですが、その多くに共通するのが「時間操作系」なんですよね。時系列をわざとぐちゃぐちゃにしてしまうタイプの作品がすごく多い。過去から未来へと続くリニア(線的)な時間軸を壊すことに、彼らは全力を注いでいる。本来ならば舞台芸術って、観客の時間と舞台上の時間がひとまず同期するからこそ、一種の共有体験が可能だったはずなんです。ところが、今やその根底が揺らいでいて、観客の時間はどんどんリニアに消費されていく一方なのに、舞台上の時間は延々と行きつ戻りつしている。こっちとしては、何だか不条理な感じもしますが(笑)。
── 時間の強制力から解放されたい欲望なのでしょうか。映画やアニメにも、
物語がループ、またはリプレイする作品が多い気がします。
ジャコ・ヴァン・ドルマル監督の『ミスター・ノーバディ』という映画は、実に巧妙に作られたループものでした。主人公が幼いときに両親が離婚する。その日が人生の大きな分岐点になっていて、それ以降は父についていくルートと母についていくルートで人生が細かく枝分かれしていくんですね。で、100歳を超えたおじいさんになった彼が、その10個以上の「ほかでもあり得た人生」のイベントをバーっと想像的に網羅していくというストーリー。人生の幸福とは何かを考えさせる、非常に味わい深い映画です。
日本にはループものは確かに多いんですが、両親の離婚から分岐が始まるというパターンは少ないような気がします。日本のループものは、基本的に恋愛至上主義なんですよ。つまり、個人の選択の問題になってくる。それに対して、両親の離婚というイベントにおいては、個人の問題を超えた家族や社会の問題がどうしても入ってくるでしょう。『ミスター・ノーバディ』の場合は、両親の離婚というショックのあとで、主人公の人生のさまざまなデモンストレーションが始まる。こういう物語の作りかたは、やはり日本とヨーロッパの大きな違いを指し示しているわけですね。
よく、日本人は空気に支配された「集団主義」だといわれますが、本当はそのベースには個人主義があると思うんです。個人主義的だからこそ、一方では古代から恋愛文学が栄えてきたのだし、他方ではひとりの寂しさゆえに集団主義=空気に巻き取られるということにもなる。昨今の日本のループものは、本質的に個人主義の文学だと思います。
── ループものの作品ですぐに思い浮かぶものといえば、『時をかける少女』ですね。初恋の想い出がループするというか。
ええ。要するに、「ほかでもあり得た」という偶然性をどこで知覚するかが問題なんです。社会や家族から偶然性を感じるのではなく、恋愛から偶然性を感じるというのが、日本のループものの特徴ですね。ただ、それもやっぱりよしあしで、確かに日本からは実験的な作品もいろいろ出てくる一方、『ミスター・ノーバディ』みたいな作品はなかなか出てこない。
── 今、日本社会に必要な神話とは、どのようなものでしょうか。
村上春樹さんや宮崎駿さんの作品からもわかる通り、日本人は資本主義や自然を単位とする神話はわりとうまく作れるんですが、国家を単位とする神話を作るのはたいしてうまくないんですね。そもそも、日本における国家は中国やヨーロッパからの輸入概念でしかない。「愛国心」なんていうのも、もとは朱子学以降の中国の概念でしょう。その点で三島由紀夫はやっぱり鋭く、古来日本には「愛」などはなく「恋」しか存在しない、だから「愛国」は日本的な概念ではない、といっている。そういうわけで、三島は「恋」の対象としての天皇を掲げるんです。ここでも恋愛至上主義が顔をのぞかせているわけですね。とはいえ、今となっては天皇を「恋」の対象として神話化するのも難しい。昭和天皇を知らない若い世代にとっては、三島の言説にはもはやリアリティがないでしょう。ただ、それならそれでかまわないわけで、日本の神話作家は、国家より小さいもの・国家より大きいものに照準を合わせていけばいいのです。
ともかく、資本主義に立脚しようと国家に立脚しようと、神話というのは多くの市民が腰かけることのできる共有スペースを作るものです。さしあたりそういうスペースがあるからこそ、それに対する批判や再構築も意味をもつわけですね。しかし最近では、自分たちの共通体験を深部まで掘り下げていく能力がてき面に落ちている。それでは世代間の分断が進むばかりでしょう。表現者は、あくまでそういう分断を突き抜けなければならない。その際に、現に存在するものばかりではなく、「ないもの」への想像力を忘れるべきではありません。ゼロ年代以降の傾向として、「現にあるもの」に対する批評は非常に盛んになりましたが、その分、不在のものを直観する能力は落ちてしまったのではないでしょうか。その「不在のもの」の力を回復していくことを、次の新著なんかを通じて地道にやっていきたいと思っています。