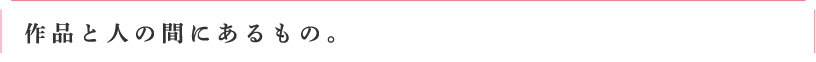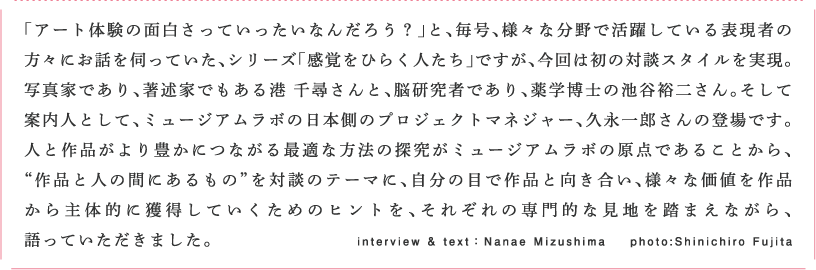主観と客観をめぐって。
── まず、ミュージアムラボを体験してみての池谷さん、港さんの率直な感想を聞かせてもらえますか?
池谷 《青い服の子供》という1枚の絵をテーマに、これだけ立体的に、知識の面、空間の面、時間の面と、多様な角度から鑑賞アプローチをかけていくのは面白いです。私は常々学生たちに、美術館に行って本物に接していい経験をするしか、直感を養う方法はないんだという話をしているのですが、実際には、美術館には自分以外の大勢の鑑賞者がいますので、思いのほか本物をじっくりと味わうのは難しいものです。しかし、このミュージアムラボの場合、予約制ということもあって、第一級の作品をただじっくりと集中して観ることができたので、それが最初の感動でしたね。より深い美術体験ができると思いました。
港 僕は恐らくミュージアムラボの展示は、これまで半分以上は観ていますが、回を追うごとに新しい技術が取り入れられていて、いつも感心して観ています。何より面白いと思っているのは、作品1点の美術館というのが新しいコンセプトだなと思いました。今も世界中の美術館では、まず量と動員数とかで勝負するところがあって、ルーヴルもその頂点に立つんでしょうけども、そのルーヴルと組んで1点だけ展示する。それも今までにないような試みで見せていて、1時間を超える鑑賞が可能だというコンセプトが僕にとって非常にワクワクするものです。
池谷 ひとつの展覧会に対して、結構期間を長くやっているものなんですか?
久永 会期は約半年間になります。毎回、ルーヴル側の担当者と議論や開発を重ねていますが、たった1枚の絵にも、こんなにたくさんの言いたいことがあることがわかってきました。またそのひとつひとつを知ることで、”こういう絵の見かたもあるんだ“と、気づくことができるんですね。そしてその見かたは、他の美術館の作品でも応用できるし、何より美術館そのものが楽しくなる。開発者として、面白い経験をさせてもらっています。
── 芸術の”見かた“は、客観的な状態の把握と、鑑賞者個人の主観、その両方が反映されて、最終的な見えかたにつながるものだと思いますが、そのなかで大切な視点とは、どんなものだと思いますか?
港 美術に限って言えば、そもそも美術館が生まれた背景は、市民革命が起こり、貴族などの収集物が大衆の共有物、資産として市民に開放された大衆社会がベースになっていますよね。ルーヴル美術館もその代表のひとつですが、この革命を機に何が起きたかと言うと、客観的な知識や判断力を重要視する教育が近代に敷かれていったわけです。まさにゴヤというのは、その一番激しい時代を生き抜いてきた画家なんですよね。僕はゴヤが本当に好きで、なかでも彼の最晩年の作品《ボルドーのミルク売りの少女》、これは何度観てもいい絵だなと思っているんですが、そんな啓蒙思想をベースとしたゴヤが、その客観の時代のなかでどう生きたかを考えると……、たとえ精神が崩壊していっても、結局最後はあくまで個人の目で画家としての責任をまっとうした、そういう人だと僕は思っているんです。
── 今日観ていただいたゴヤの生涯と作品を紹介する、デジタルシネマのタイトルも「ゴヤの目」。あくまでゴヤの視点から、作品世界を知ろうとする内容でしたね。
港 そうでしたね。美術の歴史を書いたり、研究したりするため、客観的なデータは必要です。でもこのゴヤの目、生き方のように、本来美術が求めているのは、主観だけでできていること、最後は自分の目で責任を取ることだったり、個人を信じることだったり、ということじゃないかなと思うんです。
池谷 僕はどうして主観が生まれるのか? そもそも私ってなんだろう?とか、心の成り立ちについて考えるのが好きです。でもそう考えるのも、結局私の主観にすぎないわけで、だからこそ客観性の議論が面白くなる。自分のなかの客観と呼べるものは、他人と共有されるべきものであると期待します。であれば、他者とは何か? 客観とは何か……? これは素晴らしい研究対象ですよ。つまり、なぜ脳という物体が客観性を仮定できるのかというのが面白い。でも実際にゴヤも主観で絵を描きながら、他人から見たらこの絵はどう見えるだろうか?という、客観とは呼べないかもしれないけど、でも主観とは異なる視点を持っていたと思うんです。外部に視点を置く能力は、いったいどこから来ているのか?について考えることは、もうそれだけでワクワクします。
久永 その第3の視点を上手く持つための方法とか、考え方って、池谷さんのなかにありますか?
池谷 わかったら私も教えて欲しいです(笑)。ただこれは脳科学的にではなく、あくまで個人的に気をつけていることですが……、自分の今の感覚とか、ふと浮かんできた感情などを、そのまま鵜呑みにしないようにはしています。だって、今感じていることは正しいとは限らない。物事の本質を反映していないかもしれないわけです。だから他の視点からのものの見かたはないかな?と、模索するクセを普段からつけるようにしています。もちろん、それが第3者の視点かと言われると、わからないんですよ。客観的かと言われても違う気がしますし。きっとね、今日観たゴヤの絵も5年後の自分が観たらまったく違う見かたをすると思うのです。いや、違っていなければ、それは成長していないという意味ですから、ぜひ変化して欲しいのです。だから、そういう可能性を、今から自分のなかに残しておきたいと思っているんです。
久永 確かにそうですね。我々も開発の過程のなかで、例えば「こういうものがいい」と開発者があげてきたアイデアに対して、「それ、君のお父さんはいいと思うのかな?」と、割と自分の近しい人に成り代わって考えてみるということをしています。すると、「うちの父親は目が悪いので、これでは駄目かもしれない」と、まったく別の視点が生まれて、それをまた開発に生かしていく。そんなことをふと思い出したんですが、今、池谷さんがおっしゃった”今の自分の感覚を疑おう“というのは、いろんなことに生かせる考え方ですね。
池谷 なるほど。別の言い方をすると、きっと自分で思う以上に、自分の脳はポテンシャルを持っているとも言えそうです。例えば歴史的にみても、過去では考えられないようなものが、今この時代では芸術としてみなされています。つまり、過去に比べて人々の解釈の仕方も接し方も感じ方も違うから、どんどん芸術の許容範囲が広がっている。とすると、芸術が脳の使い方を開拓してくれているのではないかと。「自然は芸術を模倣する」とオスカー・ワイルドが言っていましたけど、よく考えれば、脳も自然の産物ですから、この言葉は脳にも発展的に解釈できますよね。「脳は芸術を模倣する」と。芸術は脳の産物かもしれないけど、脳の働き方も芸術に影響を受けていることを感じます。
今、美術館に必要なこと。
港 久永さんは、ミュージアムラボの開発を進めるなかで、フランス人と接する機会も多いと思うのですが、美術の見かたにおいて、日本人とフランス人との違いはありますか?
久永 あると思います。日本人とフランス人では、ベースにある知識が違いますから。フランス人は特に美術教育を受けていなくても、例えば教会にいけば、赤い服に青いマントというとそれがマリア様である、ということが日常の一部になっているので、美術館で観る絵のなかにそういうものが描かれていても、自然と理解が進みます。でも、我々日本人には馴染みがありません。逆を言えば、お釈迦様などのモチーフに対しては、日本人の理解が早い。つまり題材にするカルチャーで、各々見えてくるものは大分違うだろうなと思います。
池谷 文化背景はなかなか共有できないものですよね。今の話を伺っていて思い出したんですが、去年にある古代遺跡を観に行ったんですよ。そこでガイドさんがこう言っていました。「日本人はガイドの話をちゃんとうなずきながら聞いてくれる。アメリカ人は、ガイドの話を遮って、どんどん質問してくる。イタリア人はずっと仲間同士で井戸端会議をしていて、見てさえいない」と(笑)。この遺跡に限らず、そもそも芸術に対する見かた自体も、国の文化背景だけではなくて、国民性すらも反映されているんじゃないのかな?と思います。
久永 違っていないと面白くないっていうのもありますよね。
池谷 西洋絵画、あるいはクラシック音楽でもそうですが、これらのルーツはヨーロッパにあります。ですから、歴史や文化が幼い頃から身についたヨーロッパ人でないと本質的な理解は難しいとヨーロッパ人たとは思っているようです。でも我々には、日本の特有感性がありますから、そのレンズを通して西洋絵画を楽しんでいます。だから思うのです。ヨーロッパ人には我々のような西洋絵画の見方はできないので気の毒ですねと(笑)
港 恐らく、今世界中の美術館がグローバリゼーションに対してどう対応するのかに追われていると思います。20世紀前半まで美術館というのは、国民の教育のために存在していて、つまりその国の歴史が、美術の歴史のなかでどう関係づけられるのか?に重きが置かれていた。でも今は世界の観光地と世界の美術館が、ほとんど同義に語られる時代です。ルーヴル美術館なんてまさにそうだと思いますし、実際、毎日様々な国から様々な民族がルーヴルに訪れています。そういうなかで当然、美術の見かたも様々出てくるわけで、だからこそ美術館側も、それに対して取り組みを考える時代に入ったと思います。
久永 おっしゃること、よくわかります。我々もミュージアムラボの開発に取り組むことは、美術館の可能性を模索しているようなところがあります。
港 去年、オーストラリアのタスマニア州に大きな美術館ができたんですね。名前がMONAと言って、Museum of Old and New Artの略ですけど、この美術館、個人で建てた最大の美術館ということで話題になっていたんですが、ここに自分の作品が恒久展示されることになって、オープニングに行ってきたんです。古代エジプト時代のミイラから、コンテンポラリーアートまで、フラットに展示している美術館なんですが、そのなかでひとつ面白いなと思ったのは、鑑賞者への作品情報の与え方です。ここのガイドはすべてiPhoneで統一されているんですが、ひとつの作品に対して与える情報を複数用意していて、それがランダムに出てくるような仕組みにしているんです。つまりもし5人のグループで作品鑑賞する場合、それぞれ違う情報を得ながら鑑賞していくことになります。確か最後、鑑賞者にアンケートを取っていたと思いますが、そのアンケートの内容を見ると、やっぱり5人それぞれ作品に対する印象が違うものになっているんですよね。それを知った5人は、ガイドからどんな情報をそれぞれ与えられたのか、後でお互いに情報交換をすればいいと。私はこれを実際に体験して、美術館の印象がだいぶ変わってきたなと思いました。今までの美術館というのは、同じ情報を入り口としていたわけですから。いいか悪いかは別として、実験としてこの美術館は非常に面白いと感じました。
再現性に対する一回性。
池谷 “一回性”は、最近の科学界でキーワードとなっています。でも、そもそも私たちの日常はすべて一回しか起こらない。今対談しているこの空間も、二度とない。真似ることはできたとしても。これまでの美術館は「あそこに行けばあの作品が観ることができる」といったような、再現性をすごく重要視して来たと思うんですね。でもそこに一回性、ユニークネスを持ってきたというのは画期的な感じがしますね。
港 きっとここのミュージアムラボが始まったということもそうだと思うんですが、今までパブリックな機能を持っていた美術館で、どれだけインディビジュアルな体験をさせるかという、相反するというか矛盾するようなことを美術館もやっていかないといけないんじゃないかと。例えばある鑑賞者には、学芸員の疑似体験、あるいはバックヤードで何が起きているのかを体験してもらうとか、そういったかなり突っ込んだ体験、そういうメニューをいくつも用意しておいて、人によってカスタマイズできる。そんな鑑賞者をプロデュースするような美術館にやっぱり変わってきているところがあるんでしょうね。つまり観客の多様性に対応していくということ。当然、リピーターというのもいるわけで、2回目、3回目と同じ絵の前に立ったときにどんな違った体験ができるとか、そういうことも含めて、体験のユニークネスというのが求められているのかなと思います。
池谷 “人がこうあるべき”、というのがやっぱりユニークネスなわけだから、やっぱり美術館の在り方も、人の存在性というか、人としての本来の原点に近づいてきているという解釈もできますよね。昔の美術館というのは、導線通りに歩いて行かなくてはいけない、入る前からもう運命が決まっているような、堅苦しいイメージがありました。今の美術館の在り方は、本当は自由はないにしても、主観としての自由度が高くて、関与感を与えてくれる。
港 ある意味で美術館の前身であった、博物コレクションとでも言うんでしょうか。その珍奇なものを集めた、あの世界にもう一度戻っていく必要があるという人もいますよね。好奇心と驚き。このふたつをどれだけ人にそれぞれ違った形で呼び起こしていけるのか?ということ。やっぱり美術館が国民の教育に特化したせいで、教科書的になりすぎた、という反省はあると思うんですよ。なので、そこから脱するというか、もう少し多様な観客に対応していかなくてはいけない。だからこそ驚きというのは、これからもうひとつのキーワードなんだろうなって思いますよね。
電化ルネッサンス!?
池谷 ミュージアムラボの最後にあった、ルーレット(※コンピュータが生成した、偶然性を利用し、《青い服の子供》の洋服・持ち物・背景をスロットマシンのように選ぶ鑑賞システム)のようなもの、あれは驚きでした。まさに一回性ですよね。
港 僕はすごく気に入っているんですけどね(笑)
池谷 あのルーレット、見かたによっては「絵画の冒涜だ」っていう人はいないんですか?
久永 もちろん、「こんなことをやっていいのか?」という人はいます。特にオリジナルの絵をすごく尊重していると、そういう意見になると思いますが、あのコンテンツは、そもそもオリジナルに対しての説明ではないんです。本物の作品が美術館に置かれると、その本物のイメージというが利用されて、別のものになっていきますよね、ということをやろうとしたものなんです。その意図は、ルーヴル側の学芸員にも理解してもらいました。
池谷 ええ、私の解釈としては、冒涜ではなく、一種のオマージュだと思いました。作品の発展性のひとつの原点を見せるわけですからね。
港 情報デザイン的に考えてみてもすごく面白いと思うんですよ。たぶん、あれ、ルーレットの変化が早かったでしょう。そこがやっぱり重要なのかなと思って。
池谷 意図した絵柄には止められませんっていう(笑)。
港 「あえて偶然性を入れるとどうなるのか?」ということだと思うんですよね。それは通常、美術館のなかだけでの体験ではできないものですよね。(《青い服の子供》の)背景を変えるということも、情報デザインという技術が生まれて初めて可能になったことですね。恐らく10年前の美術館では、鑑賞した後カタログを買って読むか、絵ハガキを買うかぐらいのことしかできなかったと思うんですよ(笑)。でも今は、ある程度絵画の前で、それもリアルタイムで、引き起こせる。そこが重要だと思います。今までの美術館は作品に対して、あまりに保守的なままできたという気がするし、もっとこうかき混ぜたいという感じはしますよね。
久永 開発をしていて自分でも不思議だなと思うのは、例えば《うさぎの聖母》(ティツィアーノ代表作。ミュージアムラボ第3回展で公開)もその当時は、解説のための絵なんですよね。その当時、人々が宗教のある概念とか伝説の内容が理解できないから、説明するために絵(《うさぎの聖母》)にしたわけです。それを今、さらにその説明をするためにミュージアムラボで装置を使って、説明している。ということは、今我々が作っている装置も、もしかすると200年後には「これは一体何なのか?」という説明装置が出てくるのではないか?と思ったりします。
池谷 いいじゃないですか。今ここで作っているものが博物館に入ったら。
久永 そのときはどんな説明をされるのでしょうね(笑)。
池谷 「あの当時はね、国民の文化リテラシーが低かったから、こんな工夫した美術解説装置が必要だった。こうした機械を使って一般市民に徹底的に啓蒙が図られたからこそ、私たちはやっと今のレベルにまでリテラシー能力があがってきたんだよ。人がやっと人にになった、その最初のステップこそが、この装置なんだ」、なんていう風に将来紹介されたら、嬉しいですよね(笑)。
港 でも今回ミュージアムラボで開発された鑑賞システムの一部が、来年の6月にルーヴル美術館に入るわけですよね。そのこと自体、画期的だと思うんですよ。というのは、僕のように情報デザインに取り組んでいる側からすると、情報デザインそのものも、ひとつのアートワークですから。そのアートワーク、つまり鑑賞システムが、200年前の作品と一緒に展示されることになるわけでしょう。それはルーヴルにインタラクティヴなメディアアートが展示されるわけで。これもある種、観客も参加できるインタラクティヴの模写だと思うんですけど、その模写をしながら過去の作品を次の未来に受け渡す、という、そういう意味でのアートワークと考えてもいいんじゃないですか。後世から観たら、「変わったことやっていたね」と思われるのでは(笑)。
池谷 電化ルネッサンスだ(笑)。
久永 そう捉えられますね(笑)。
池谷 あともうひとつ感じたのは、私の実験のお話になって申し訳ないんですけど、ネズミのヒゲの反応を僕らは研究しているんです。ちなみにネズミのヒゲは、人の指先ぐらい敏感です。このヒゲに、例えばざらざらしたものが触れると、“触れた”という反応が脳から記録できるんです。この実験を何度もしているとね、時々ネズミが自らひげを動かして触りに来ることがあるんです。で、そういうときのネズミの脳の反応が、10倍ぐらい強いんですよ。つまり、同じものを触るにしても、ネズミの方からアクティヴに情報を仕入れにいったときの反応の強さの方が、ものすごいということ。何が言いたいのかというと、まさにこのミュージアムラボは、アクティヴな場所じゃないですか。身体を通じた、インタラクティヴ性が重要視されている。だから脳の仕組みから考えても、これは身体性の復興、ルネッサンスですよね。個人的には、展示質にあった「絵画の物質性」(※体験レポート写真3で紹介しています)をテーマにしたコーナー、いいですよね。ぶっちゃけてしまうと、操作スイッチとなっているあのブロック、実質的には要らないじゃないですか(笑)。ボタンでも代用できるし、下手したら盗まれかねないものを、あえて用いるということ。一見余計なものをテマヒマかけて作って、鑑賞者に手にしてもらうエナクティヴなコンセプトところが、個人的には特に好きですね。
感性と知性と。
── ひとつの作品を目の前にして、人それぞれに好む、好まないという感情が生まれます。そもそも人が作品に対して抱く感情というものは、どこで生まれ、育まれているのでしょうか。
池谷 好き嫌いはあまり理屈にはならなくて、どちらかといえば動物的な勘、つまり直感ですよね。直感の多くは過去の経験の集積から生まれるものです。例えば幼い頃の経験はずっと脳に痕跡として残っていて、それが直感を働かせるときに利いてきます。ただ人は少し特殊。動物は一度嫌な経験をすると、もうだめなんです。人は言葉を持っているから、「本当はね」と説明すると理解しあえる。あるいはビールは最初苦いと思っても、やがて美味しいと思えたりするように、人は好悪を克服することができるので、好みの傾向が変わります。港先生は日々たくさんの美術作品をご覧になっていますよね。そんななかでも、自分の好みは今でも変わってきているという感じはありますか?
港 まだありますね。例えば、嫌いな映画を好きになったりすることがあります。そういうときは、ひとりのときではなく、人にその映画について話しているうちに、「あれ? 意外と俺、この映画好きだったかもしれない」という感じ。それはしょっちゅうあります(笑)。
池谷 先生もそうなのですね。面白いです。脳のなかには”好きだ“という快感を担当する場所が、大雑把に言うと、2カ所あります。ひとつは、テグメンタと言われるエリア。例えば食事をしていて”美味しい“、赤ちゃんを見たときに”かわいい“とか、そういった本能的な感情はテグメンタが担当しています。もうひとつは、長い名前なので敢えて言いませんが(笑)、前頭葉の下面のところ。ここが感じる快感は、本能的なものではなくて、いわゆる知的理解からくる快感。芸術系はまさにここで感じているんです。いろいろと研究していくと面白いんですが、実はワイン好きが「このワインは最高ですね~」なんて言うときの快感もまた、芸術系と同じ快感なんですよ。ワイン好きの皆さんって「ボルドー地方のどのシャトーの何年のワインだからね」などと語り合っていませんか? つまりワインへの知的理解からくる快感なんです。
港 僕もまったくその通りだと思っていて、この好き嫌いを伴う直感を感覚や感性という言葉で説明すると、なんとなく捉えどころがなくて、とてもインディビジュアルなものという風に思いがちなんですけど、でも実は一番そこに可塑性がある。例えば”好き“っていう好みの感覚というのは、お互いにリンクしているものでもあると思うんです。どういうことかと言うと、例えば恋人とのデートで絵の展覧会を観に行ったけれど、その内容に関して僕は好きじゃなかった。ところが相手が「私はこの絵を好きだ」と言う。人間の脳というのは、好きな人が好きと言っているものは、いいのかもしれないって思うところがありますよね。ワインもそうですが、つまりそれは情報を共有するということに行き着くと思うんですけど、知的な回路を通して、好みがどんどん変わっていくというのが、ひょっとすると人間の一番面白いところなのかもしれませんね。
久永 まさにおふたりが今、お話しされたようなことに通じることが、先日ワインを扱う企業の方と話題になりました。その方がこう言っていたんです。「ワイン好きがワインを最高だって思うときというのは、自分が知っているボキャブラリーを最大限に活用して、”こうだろう“という予想をしたワインが、実際に飲んでみても想像通りの味わいで、かつ自分のそのボキャブラリーのなかにピタッとはまっているときで、それがもう最高に嬉しくて楽しい」と。だからワインとは、飲めば飲むほど、ボキャブラリーが増えていけばいくほど、楽しくなっていくらしいんです。
港 その話も非常に腑に落ちますよね。我々は感性と知性を別のものとして捉えていますが、実は感性のかなりの部分は知性で説明できるというか、知性でできていて、逆に知性のある部分は相当感性でできている、というその重なりの部分がすごく大切なんじゃないのかなと、最近思うようになりました。
池谷 感性を重要視する人は、「そんなもの理屈で説明してはだめだ、言葉で説明してはだめだ」と言うことが多いように感じます。もちろん、そう言いたい理由はよくわかりますし、実際、ある部分ではそれは当たっているようにも感じます。でも、私たち人は言葉を使って考える動物です。感性や理解力はボキャブラリーに影響を受けるんですよ。例えば、マニフェストとかコンプライアンスとか、新しい言葉が導入されると、私たちは新しいコンセプトを思考パターンに含めることができる。結果、成長とともに思考はどんどんと複雑になり、多様になる。それが脳の生理であるなら、当然、言葉にしてみることの面白さがあると思うし、それによって自分の感性が磨かれることは、悪いことではないかと。だから今、港先生が「感性と知性の重なりの部分がすごく重要だ」とおっしゃっていましたけど、芸術を楽しむことのひとつに、自分の感性と知性とを遠慮なくぶつけあうことがひとつの楽しみになりますよね。
久永 思えばミュージアムラボでも、感性と知性、その両方を養ってもらえるような場づくりをしてきたんだなと、おふたりのお話を伺っていて気づかされました。この対談では、本当にいい刺激を受けました。これからもそんな快感を得られるミュージアムラボを目指して頑張っていきたいと思います。