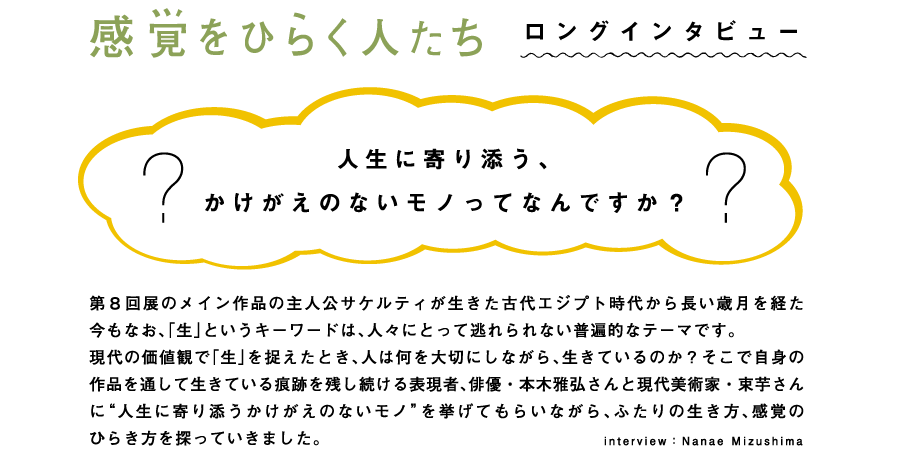恩師からふいに手渡された本が、
今ではお守りのような存在に。
—今回の企画で挙げていただいた、時計(写真)。とてもチャーミングで素敵ですね。
この時計は自分が5歳ぐらいの頃に描いた絵をコラージュして、後にシルクで刷って時計にしたものです。絵の周りを囲んだ文字はお経の一部。幼かったので当然お経の内容もわかりません。視覚的に文字を捉えて、描きたいものに出会えた感動のみで筆を進めていたんだと思います。その感動が文字からも強く感じ取れるので、すごく気に入っているんです。
—絵を描くことは幼い頃から好きだったんですか?
そうですね。私は6歳になるまで、絵を描くのがとても好きな子供でした。だけど小学校にあがったぐらいの頃から絵を描かなくなったんです。きっかけは、当時描いた絵を母に褒めてもらえなかったから。今でもよく憶えているんですが、ある日ディズニーに登場するバンビの絵を描いたらすごく上手に描くことができたので、早く見せたくて母の帰りを楽しみに待っていたんです。でも実際見せたら全然褒めてもらえなかったんですよ。それが本当にショックで、以来全然絵を描かなくなってしまいました。その頃、私は“誰かに褒められる絵を描かなくてはいけない”って思うようになっていたんです。
—親の意識を自分に向けたいっていう純粋な子供心が、思わぬ方向に束芋さんを向かせたんですね。
だから中学でも高校でも、美術と向き合うことを避けて過ごしていました。それが一変して再び絵と向き合うことになったのは、大学進学を迎える頃。大学には行きたい。だけど私は何せ勉強ができない子だったので(笑)、それで再び美術に目が向いて、高校3年の夏、美大を受けることに決めました。その後1年浪人して京都造形芸術大学に進学。大学では様々な技術を学んで、とても楽しい学生生活を送っていましたけど、時計の絵を描いていた頃の純粋な感覚は、やっぱりあの当時だけのもの。そういう意味でもこの時計の絵は、自分の原点とも言える、とても大切なものなんです。今でもアトリエに置いて利用していますよ。時間もよく狂うんですけど、そんなところも含めて好きです。
—もうひとつ挙げていただいたのが、束芋さんの学生時代の恩師、田名網敬一先生(※1)の著書『人工の楽園〜田名網敬一のシネ・マーケット』ですね。
この本は田名網先生があるときふいに私に手渡してくれた本ですが、今では何かに迷う度に手に取っています。誌面に載っている田名網先生の作品はもちろん、やんちゃだった頃の田名網先生の顔写真を眺めていると(笑)、なんだかこう、自分自身、初心に戻れるんですよ。
—初心に戻る、または戻りたいって思うことはよくあるんですか?
作品制作をするなかで、初心に戻ることは大事なことなんです。最初の発想から時間が経つにつれてどんどん頭のなかに余計な考えが入り込んできてしまって、最終的にはその作品に本当に必要なものがわからなくなるぐらいぐちゃぐちゃになってしまうこともあるんです。すると前にも進めなくなる。そういうときは、最初の発想に戻ってみたり、究極的にはその発想自体も捨てて、ゼロから考え直すということをするんです。そのゼロにするときのお守りみたいな存在が、この本です。田名網先生は、存在自体も私の人生において重要人物なんですよ。
—それは具体的に言うと?
学生時代も今も、人生の大切な分岐点で歩むべき方向を指し示してくれるような人です。大学の授業では表現の発想方法を教えていただきました。普通の大学ならひとつの答えに導いていく授業が多いと思うんですが、ひとりひとり(学生)、発想の方法は違うという前提に立った上で、個々の方法論の深め方というものを、私たちに与えた課題のなかでちゃんと体験させてくれるんです。その体験がなければ、今の自分の作品はなかったと思います。適当に見える部分もある田名網先生ですが(笑)、決して深刻ぶらずに意見を下さるので、そこが信頼できるし、今でも田名網先生に「いいんだよ」って言われるだけで、私は安心して自分の道を進めるんです。
大切な人との意見の違いが、
結果的に自分の感覚をひらいてくれる。
—束芋さんにとっての“道”とは、何を指すものでしょうか。
私にとって自分の道とは、“今”を選択することなんです。今現在自分の周りにあるものや状況、自分の感覚すべてを使って選択していけば、ちゃんと納得のいく答えは出ると信じているし、すべてを受け入れられる。だから作品を作るときも、いつも“これが最後かもしれない”という気持ちを持って作ります。“始まって終わるんだ”ということを覚悟することで、精一杯その作品と向き合える。先のことを考えると出し惜しみじゃないですが、計算が入ってきてしまうんです。
—つねに一歩先を見据えて行動している私たち人間にとって、今の“ど真ん中”で生きるということは、意識をしないとなかなか難しいことなのかもしれません。
時々両親には「もっと人生を俯瞰して見て、深い考えを持たなくてはいけない」って言われたりすることもあるし、討論になります。でもどんな選択であろうと、今自分がした選択を正しいと思えることが、私にとっての幸せ。今を深めていくことが、人生の深さ、そしてその選択が“明日”を与えてくれていると思っています。
—束芋さんの場合、作品が残る。作品そのものがすでに明日を作っていますね。
本当にそうです。たとえ作家本人が死んでしまっても、作品は生きることができる。でもそこで生きていけるかどうかは、何より作品を引き継いでくれる人たちのケア次第。私はすでに安心して作品をお任せできる美術館のキュレーターの方に国内外ともに出会えているので、それは本当に幸せなことです。その方たちは作家の想いを汲んだ上に、当たり前のように100年後、200年後の作品の状態を考えてケアしてくれています。作品を作るということは、受け継がれることへの期待も持つことができるんです。
—作品が幸せでいられる場所があるということは、とても大きなことですね。
例えば私の作品『にっぽんの台所』は、大学生の頃に作った作品ですが、今はだいぶボロボロなんです。作品に必要な素材も、当時手に入るものでしか作れていないですし、完成後のケアもしっかりできていない部分もあったので、これ以上の海外遠征は難しいかな?と感じるほど。でも実は『にっぽんの台所』は、このまま朽ちていってもいいとも思っているんですよ。そうなったとき、それこそ信頼しているある国内の美術館であれば、『にっぽんの台所』はよい余生を送ることができるんじゃないかなって。100年後残っていなくても最期の時をいいカタチで生きていってくれたら……。そういう場所があるのは、ありがたいです。
—最後に、束芋さんにとって表現者としての新たな気づき・次に進むための一歩はどんなところにありますか?
人と意見が対立したりケンカしたときが多いかもしれないです。ケンカした直後って、“自分は間違った発言をしたのかどうか?”ということをかなり長時間考えるんですよ。と同時にそういうときは、必ず対立した相手のことも考えます。相手とはここの部分が違うから、こういった考えが自分のなかに出てきたんだとか、自分はこういう考えだから、あの言葉が口から出てきたんだとか、突き詰めていくうちに少しずつ気持ちの整理がされてきます。すると最終的にはその対立やケンカが、自分の人生のコマをひとつ進める行為であったと気づくんです。相手と自分との“ズレ”というのが、結果的に自分の個性を見いだすきっかけになるんです。