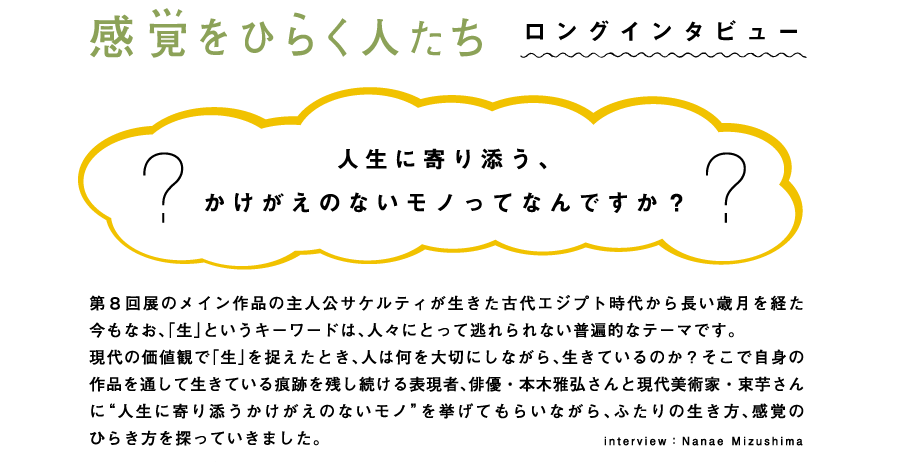力強く生命を営む枇杷の木を見ると、
一時でも自分はフラットになれる。
—本木さんの立ち振る舞いには、いつも知性とエレガントを感じます。そして自分の感覚を大切にしながら、ひとつひとつの作品にとても真摯に向き合っている。そんなイメージも持っています。きっと確固たる信念みたいなものをご自身のなかに持っているのではないかと、感じているのですが……。
残念ながらそんな立派ではないですよ。10代の頃から芸能の世界で活動をしていますが、その職業柄もあるのか、日々、現実と虚構の世界を行き来しながら生きているような感覚があるんです。だから例えば“自分が一体何者なのか?”などと考えても人としての生々しい実感が薄くてどこかこう、常に根無し草的であるし、時に虚無感を抱えてしまうことに繋がっていきます。
—本木さんは役を通していろいろ人生を生きています。でもそれは見かたを変えれば虚構の世界でもありますよね。
だからこそ今回の企画、自分の原点になるモノ、普遍的に大切にしているモノについて尋ねられたとき、照らし合わせていろいろ考えてはみたものの、やっぱりその根無し草的な意識のせいか、正直どれもしっくりとこなかったんです。役者をしている都合上、役が変わる度にこだわるモノも一変しますしね。原作や台本、資料や噂話など、撮影中は自分が演じる役に関わる情報すべてが、何より大切なモノになりますから。
—はい。こちらがお願いしておいて恐縮ですが、モノを挙げていただくことは、簡単なことではありませんでしたね……。
同時に日常生活では、東日本大震災によって自分自身は、“生きる”ことへの問いを突きつけられました。自然エネルギーの課題なども、自分ひとりで考えがまとまる規模ではないけれども、もう絶対に無視はできないという状態です。そういうなかで被災された方も、自分も含めた被災していない方も、ひとりひとりが自分なりの価値観を再構築しながら、なんとか納得のいく着地点を必死に模索している。自分も子供を抱えてそういうことを考えていると、とにかくきりきりと胸が痛む毎日です。
—子供が大人になったずっと先の未来のことも想像してしまいます。
そんな日々のなかで例えば「今から30分後に大地震が起きます。人間のほかに大切なものを2つだけ持っていくことができます」と言われたら、自分は何を選択するのだろうか?と、少し想像してはどきどきしてしまう。ということで、役者の自分、家族といる自分、両方の立場から考えてみても、大切なモノには順位がなく、安易に選択できません。だから非常に悩みました。と、前置きが長くなってしまいましたが(笑)、そんな風に考え続けるなか、なんとか……なんとかひとつ、腑に落ちるモノが見つかりました。「枇杷の木」です!
—「枇杷の木」! 予想もしないもので……。
はい。それも日々成長を遂げる過程にある枇杷がいい。自分は渋谷という騒々しい都会に住んでいますが、自宅には細々とした空間ながらも、家を囲む形で庭があるんです。その庭には山桃や桜の木、金柑やローズマリー、ラベンダーなど、いろいろな植物が生息しているんですが、まさに枇杷の木もこの庭で育ったもの。今の場所に住み始めて15年ですが、毎年繰り返し実をつけています。むくむくと実を膨らませ成長する枇杷ですが、その姿はとても淡々としています。でもふとそんな枇杷に意識を向けると、どんなに自分の環境や心情が乱れていても、一時、フラットになれる。養老孟司さんの言葉を借りると、“人間も自然の一部”ということでしょうか。もっと言えば、自然をはじめとした、身近な存在に対する素直な目線を忘れたくない……という意志が生まれます。
—つい“人間”と“自然”と、切り分けて考えがちなところってあるんですが、確かにそうですね。
相手(枇杷)は何も主張していないんですよ。毎年変わりなく、たくましく生命を営んでいる。それはある種、自分の理想の姿にも思えました。しかし現実の自分には、枇杷のような平常心が足りない(笑)。だからこの枇杷にちょっとすがっているところもあるのかもしれません。そんなことも含めてこの枇杷の姿は、今の自分にとって、感覚をひらいてくれるエネルギーをたくさん持っていると言えます。まわりくどいですが、つまりどんな状況下でも、自然をはじめとする身近な存在に対しての素直な目線を忘れたくない。ということなんです。
—今お話を伺っていて、私自身も植物に対する見かたが変わりました。
ちなみにこの枇杷をポンッとテーブルの上に置いて、「ちょっとこの枇杷を鉛筆でもいいから軽くデッサンしてみて」なんて、11歳の娘にお願いして描いてもらったり、裸の1歳児がこの実を踏みつけた瞬間をカメラに収めれば、我が家のなかではそれらが最高のアート作品にもなるわけですよ。子供が冗談みたいに絵の具をこぼして広げたものを観て、“これとジャクソン・ポロックの作品と一体なんの違いがある?”って、本気で思ってしまいますから(笑)。
家族と過ごす時間そのものも
アートだと、体感する日々。
—本木さんは普段からアート鑑賞はされますか?
20代の頃はジャン・コクトーにはまったり、国内外のギャラリーにも随分と行っていたと想います。その当時は普段も六本木WAVE(音楽を中心とした文化発信拠点。1999年閉店)やオン・サンデーズ(ミュージアムショップ)にもよく通っていたんですが、いつもふらりと足を運んでみると、必ず好みの作品に出会うんです。そこでアート関連の情報も吸収していました。まさにこの「感覚をひらく」のようなフリーペーパーもたくさん置いてあったりして。
—カルチャー感溢れる空間だったことが、想像できます。感度の高い人たちが通っていたんでしょうね。
若い頃というのは、アンテナ張っている自分を他人にアピールしたい、みたいな部分ってあるじゃないですか。自分自身もそういう道を歩んだ時期がありました。でもその道の過程のなかで、藤原新也さん(写真家・文筆家)の『メメント・モリ』に出会い、それをきっかけにインドへの旅があり、それがめぐりめぐって、映画『おくりびと』に繋がっていくんです。
—ちなみにWAVE全盛期後も、変わらず好きな音楽やアートを吸収する日々に?
いえ、WAVEがなくなったと同時に、なんとなく音楽さえも買いに行くのが億劫になってきてしまって。ファッションもそうですが、徐々に力みを減らして内的な爆発、充実を生活のなかに求めていったような感じですかね。また、今現在のことでいうと、家族ができてからは生活、子育てのなかで相当シュールな体験を内々でたくさんするので、逆に外に向かってアートを求めることは本当に少なくなりました。
—そんななかで、今もずっと変わらず好きなアート作品はありますか?
サイ・トゥオンブリは、美しい色合いと間の良さが好きで尊敬しています。
それからスイスのローザンヌにある「アール・ブリュット・コレクション」(※1)は好きですね。今まで3回は行っています。この前、原宿のラフォーレミュージアムで展覧会があったヘンリー・ダーガーもアール・ブリュットですよね。特異な環境のなかで人の内側からつきあがる衝動のままに表現された芸術は、ひとつひとつが現実を超えていて、もう、いつ観ても不思議な衝撃が胸を打ちます。
—アート作品と向き合うときに意識されていることはありますか?
人生のコンディションによって、求めるアートも変化していくことが自然だと思いますが、あえて言えば、あまり構えない、ということですよね。それは人と向き合うときも同じです。これは理想です(笑)。実際、人にも作品にもまったく構えず、差別なく、何ひとつ威圧感も与えない人っているじゃないですか。あれはある種の才能であり、究極的わがままな生き方でもあると思うんですが、自分自身、そうやって構えず柔軟性を持って接したいという憧れがあります。結果、その対象に素直に愛着が持てるか否かが大切な気がします。たとえどんなに神々しいアート作品があっても、扱いに困ってしまったら、気持ちも離れていく。作品に触れながらそれへの愛着を育てられるどうか。つまり、長く深い付き合いができたら、自分にとってはその作品は本物になるのかな思います。
—また新しい愛着が持てるアート作品に出会えたらいいですね。
さっきの話に戻るようですが、やっぱり日々の生活も子育ても常に現実、現実の襲来で、やたら窮屈で、時に愉快で、“家族との時間そのものがアートでしょ!”って言いたくなるところがあるんです(笑)。でもそもそもアートって、“生きる”ことそのものを含んでいるもの。だから自分にとって思わぬ作品と出会って心震える体験も、家族との暮らしのなかで巻き起こる事態も、自分にとっては同じ一線上にあって繋がっているのかもしれません。
※1…「アール・ブリュット」とは、既存の美術や文化潮流とは無縁の文脈によって制作された芸術作品を指し、英語ではアウトサイダー・アートと称されている。精神科病院の患者、社会不適応者、受刑者など、アウトサイダーと呼ばれる人々が作者となる。「アール・ブリュット・コレクション」は、アール・ブリュットの概念を提唱したフランスの画家、ジャン・デュビュッフェが蒐集したコレクションをもとに発足した、スイスのローザンヌにあるアウトサイダー・アートの美術館。