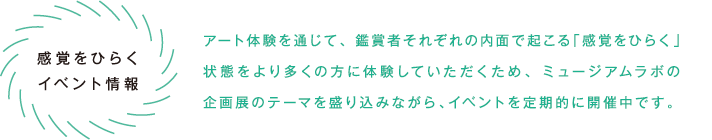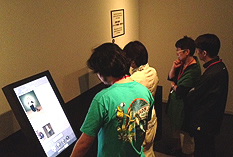第5回
『なぜ? 男は集い、酒を飲むのか
〜古代ギリシアから立ち飲みバルまでの事情〜』
ギリシア神話の一場面が描かれた第10回展のメイン作品、《アンタイオスのクラテル》(壷)。これは当時、お酒を飲みながら政治や恋愛などさまざまなことについての談義を楽しむ男性だけの宴会、「シュンポジオン」(現代のシンポジウムの語源)で、葡萄酒と水を混ぜるために使用されていたものです。今回の「感覚をひらくイベントvol.5」にお迎えしたのは、著述家の湯山玲子さんと、世界の酒場文化や、古代ギリシアにも造詣の深い小説家の島田雅彦さん。湯山さんのナビゲートのもと、ホモソーシャル概念(男性同士の強い連帯関係)などさまざまなトピックについて、古代ギリシアと現代を行き来するトークが繰り広げられました。